スタッフブログ
薬剤師の仕事・働き方・キャリアに関するトピックスから、最新の薬剤師求人、派遣や単発派遣に関する法律やルールまで。薬剤師の最新事情に精通したアプロ・ドットコムのスタッフが、就職・転職に役立つ記事を配信いたします。
派遣の基礎知識
2025.03.07
派遣薬剤師の福利厚生制度 正社員との違いが知りたい!

- 薬剤師
- 派遣
- 求人
- 正社員
- 派遣会社
- アプロ・ドットコム
- 福利厚生
産休・育休は取れるのか、有休はあるのかなど、仕事を探す際に考えるのは給与だけではありません。派遣社員は福利厚生制度が利用できないという誤解も多く、福利厚生が充実しているからという理由で正社員を選ぶ人もいるかもしれません。
実は、派遣薬剤師も福利厚生は利用できます。ただし正社員とは違う点もあるため、条件などをきちんと理解して上手に利用したいものです。この記事では、正社員との違いをふまえて派遣薬剤師の福利厚生制度について解説します。ぜひ参考にしてください。
目次
福利厚生とは
そもそも福利厚生とは、賃金や給与にプラスして、従業員やその家族の生活をサポートするために企業が提供するものです。厳密には福利厚生には「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。
「法定福利厚生」とは、法律によって義務づけられている福利厚生です。企業や従業員が一定数以上いる個人事業所は導入することが義務化されています。一般的には「社会保険」と呼ばれている健康保険、雇用保険、介護保険、労災保険、厚生年金保険を指し、雇用形態に関わらず所定の条件を満たしている場合や、申請があった際に適用されます。
一方、「法定外福利厚生」とは、住宅手当や通勤の交通費など法定福利厚生以外に企業が独自で追加提供している福利厚生制度です。法律で定められているわけではないので、制度の実施可否は企業に任せられています。
派遣薬剤師の福利厚生は正社員と何が違う?
それでは、派遣薬剤師と正社員では福利厚生にどんな違いがあるのでしょうか。
・派遣薬剤師は登録している派遣会社の福利厚生が適用される
企業に直接雇用されている正社員の場合は、働いている企業の福利厚生が適用されます。一方で、派遣会社に登録して派遣先企業で働く派遣薬剤師は、派遣先の企業ではなく登録している派遣会社の福利厚生が適用されます。
・法定福利厚生を利用するには適用条件を満たす必要がある
フルタイムで働く正社員の場合、基本的に社会保険などの加入条件を満たしているため全て適用されます。派遣薬剤師の場合は、企業に義務づけられている項目であっても条件を満たしていないと適用されなかったり、内容が違っていたりします。
・福利厚生の充実度は派遣会社によって変わる
基本的に社会保険や法定休暇などに差はありませんが、それ以外の福利厚生は派遣会社に限らず企業によって変わってきます。派遣薬剤師の場合、同じ業務、同じ職場で働いているとしても、派遣元である派遣会社によって福利厚生の内容は違ってくるため、充実度も変わってきます。
ここからは、違いをふまえながら具体的な内容をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
社会保険(法定福利厚生)
一般的に次の5種類が社会保険と呼ばれるものです。病気、ケガ、失業、出産、死亡、老齢、障害などの生活を脅かす事態に対して、一定の経済保障で生活をサポートするセーフティネットの役割を果たします。
・健康保険
病気やケガ、出産などで医療機関を利用する際に、金銭的サポートをする公的医療保険です。下記の条件を満たした社員とその社員の扶養家族が加入対象で、治療代や診察代の自己負担額が3割になります。また、高額療養費の支給や傷病手当金、出産育児一時金などの支給も受けられます。
・正社員、法人の代表や役員
・週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員等の通常の労働者の3/4以上
または
・上記を満たしていないが、従業員数51人以上の企業に勤務し「週の所定労働時間が20時間以上」「月額賃金88,000円以上」「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」「学生ではない」を全て満たしている
保険料は雇用企業と社員で半分ずつの負担になりますが、保険料は会社が加入している健康保険組合によって異なります。なお、「従業員51人以上の企業に勤務」という条件は、2027年10月に撤廃される見通しです。
・介護保険
雇用形態に関わらず、健康保険に加入している40歳以上の被保険者は加入が義務づけられている保険です。40歳になると自動的に保険加入者となり、健康保険料とセットで介護保険料が徴収されます。介護が必要になった際には、自宅や施設で介護サービスを少ない負担額で利用することができます。
・厚生年金保険
一定期間保険料を納めれば、基本的には65歳以上で年金として受給できます。下記の条件を満たしていれば加入対象になり、老齢厚生年金、被保険者が死亡した際に遺族に支給される遺族年金、障害を負った際に支給される障害年金などが老齢基礎年金に上乗せされます。
・正社員、法人の代表や役員
・週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員等の通常の労働者の3/4以上
・70歳以下
または
・従業員数51人以上の企業に勤務しており「週の所定労働時間が20時間以上」「月額賃金88,000円以上」「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」「学生ではない」を全て満たしている
派遣薬剤師の場合は派遣会社の規模、年収、勤務時間、契約期間などで条件を満たしている場合にのみ適用されます。健康保険同様、「従業員51人以上の企業に勤務」という条件は、2027年10月に撤廃される見通しです。
・雇用保険
企業の倒産による失業や自己都合での退職の際に、生活保障や再就職に向けた支援を行うための保険で、失業手当、再就職手当、教育訓練給付などが支給されます。雇用形態に関わらず下記の条件を満たす場合は加入対象になり、副業・兼業の場合でも、各雇用先で条件を満たせば適用対象です。
・1ヶ月を超える雇用見込みがある
・週の労働時間が20時間以上
・学生ではない
手続きは雇用する側が行います。派遣薬剤師の場合は契約内容によるので、派遣会社に確認しましょう。
・労災保険(労働者災害補償保険)
労働者を守るための保険です。業務中や通勤中に事故などに遭い、怪我や病気、傷害、を負ってしまったり、死亡してしまったりした場合に、本人や遺族が一定の給付金を受け取れます。在宅ワーク中の事故も、業務との関連性が認められれば労災保険の対象です。
企業規模や業種、雇用形態などに関わらず、全ての労働者に加入義務があります。加入条件などもなく、保険料は全て企業が負担します。
社会保険に加入するメリット
厚生年金保険に加入することで、国民年金に加えて厚生年金が受け取れるので年金の受給額が増えます。また、健康保険に加入していれば、傷病や出産などの手当金が支給されます。
国民年金や国民健康保険の保険料は全額自分で負担しなければなりませんが、厚生年金や健康保険に加入した場合は、一定の保険料を企業側も負担します。社会保険に加入することで就業中の不安や経済的負担が減り、将来的な補償も手厚くすることができます。
法定休暇
労働基準法や育児介護休業法などの法律により、取得が認められている休暇のことです。請求があった場合、企業は必ず休暇を認める義務があります。
多くの企業が法定福利厚生として扱っている法定休暇・休業
社会保険には含まれませんが、多くの企業で福利厚生の一環として扱われている休暇・休業です。
・有給(年次有給休暇)
一般的に「有給」と呼ばれており、所定労働日に働かなくても賃金が減ることはありません。雇用形態に関わらず、継続勤務が6ヵ月以上あり、全労働日数の8割合以上を出勤していれば、1年ごとに一定の日数が取得できます。継続勤続年数によって1年に付与される有給休暇日数が決まっています。
派遣薬剤師のように働く時間が短くても有給は取得できますが、日数が異なります。週の所定労働日数が4日以下、かつ所定労働時間が30時間未満の場合は、週の所定労働日数と1年間の所定労働日数を基に、継続勤続年数によって有給付与日数が決められています。
・産休(産前産後休業)
雇用形態に関わらず、法律で取得が認められている制度です。産前休暇取得するかどうかは任意で、出産予定日の6週間前から取得可能です。産後休暇は出産後、8週間取ることが義務づけられた休暇です。ただし、医師の許可と本人の希望があれば、産後6週間以降から働くことができます。
・育休(育児休業)
子どもが1歳になるまで、男女の区別なく取得できます。それ以降で保育園などの預け先が見つからない場合には、最大で2年間まで延長可能です。取得基準は企業の就業規則によって変わってきます。また派遣薬剤師の場合は、産休・育休中に派遣先との契約が切れてしまうと取得できなくなる可能性もあります。
・その他の法定休暇・休業
その他、雇用形態・勤務形態を問わず、働く全ての女性が取得できる「生理休暇」、要介護の家族をサポートするために取得できる「介護休暇」「介護休業」なども法定休暇です。小学校入学前の子どものケガや病気の際の通院・看護のための「子の看護休暇」、子どもの出生後8週間の間に最大4週間の休業が取得可能で、主に男性が利用できる「出生時育児休業」などがあります。
企業独自の福利厚生(法定外福利厚生)
企業の負担が法律で定められている法定福利厚生以外に、企業が任意で追加して独自に提供する福利厚生です。
・財産形成
ストックオプション制度や財形貯蓄制度など、直接的に給料を上げるのではなく、貯蓄支援やマネーリテラシー向上などを目的とするものです。長期的なキャリア形成の支援する目的であるため、主に正社員に向けた福利厚生です。
・食事補助
社員食堂やお弁当の提供など、社員の健康面の観点から食事補助をするものです。派遣会社の場合は、提携の飲食店などが優待で利用できることもあります。
・休暇・働き方
夏季・冬季休暇など、ワークライフバランスの向上を目的に設けられた法定休暇以外の休暇です。またフレックスタイム制度やノー残業デーなどを設けている企業もあります。派遣の場合は法定休暇以外の休暇はありませんが、残業の有無などを選ぶことができます。
・住宅補助・交通費
経済的サポートとして家賃や住宅手当、社員寮や社宅の提供、通勤手当や駐車場の補助などを行う企業もあります。派遣薬剤師の場合は時給に交通費が含まれることも多く、住宅補助などはありません。しかし、求人によっては社員寮の提供や住居付きもあります。
・健康・医療
定期健康診断や人間ドックの実施、健康相談窓口の設置など、身体的・精神的サポートで働く環境を整えるものです。健康維持のためのジムの利用補助やカウンセリング制度などを設けている派遣会社も見られます。
・育児・介護の両立支援
社内保育園・託児所の設置や独自の育児休業延長制度など、家庭と仕事の両立ができる環境を整える目的のサポートです。保育園の利用料の全額補助やベビーシッター割引など、育児や介護支援に前向きな派遣会社も増えています。
・自己啓発・能力開発
海外研修の補助や資格取得支援など、社員のスキルアップを目的としているものです。派遣薬剤師はスキルが重視されるため、就業前の教育制度や資格取得のための研修制度、キャリア支援などに力を入れている派遣会社もあります。
派遣薬剤師で働くなら福利厚生が充実した派遣会社を選ぶのがポイント
一般的には正社員のほうが福利厚生は手厚いといわれます。それでも最近では、働き方改革や法律改正などにより派遣の待遇改善が進み、福利厚生に力を入れている派遣会社が増えています。とはいえ、法定外福利厚生は企業が独自に行うものなので、派遣会社によって福利厚生の内容は異なります。派遣薬剤師で働くなら特に次のポイントをチェックしましょう。
・薬剤師賠償責任保険
薬剤師の業務は人の命に関わる業務です。どんなに細心の注意を払っていても、投薬や服薬指導などのミスが起こってしまうかもしれません。業務中の備品の破損・汚損なども含め、賠償責任が発生した場合にカバーするのが薬剤師賠償責任保険。加入の有無や費用の負担率などは派遣会社によって変わりますが、薬剤師賠償責任保険に加入できる派遣会社を選べば安心です。
・研修制度や資格取得支援
派遣薬剤師は一般的にスキルを求められます。未経験やブランクがある人に向けた就業前の教育制度が充実していたり、認定薬剤師の資格取得に向けた研修制度やキャリア支援に力を入れていたりする派遣会社もあります。
業界に特化しているからこそ薬剤師に嬉しい福利厚生が充実
薬剤師業界に特化して25年以上の実績を持つ「アプロ・ドットコム」は、社会保険(条件を満たす場合)をはじめ、有給・産前産後休業・育児休業などを取得できます。年に1回の定期健康診断は無料で受診でき、産業医による医療健康相談も行っています。薬剤師賠償責任保険も完備しており、費用はアプロが全額負担するので安心して働けます。
教育・研修制度も充実しており、受講すると勤務扱いになり給与も支払われます。スキルアップのためのeラーニング講座は1,100種類以上あり、基礎的な講座はもちろん、業務に直結する講座が揃っています。派遣薬剤師として働きたいと思っている方は、「アプロ・ドットコム」の無料サポートをご利用ください。
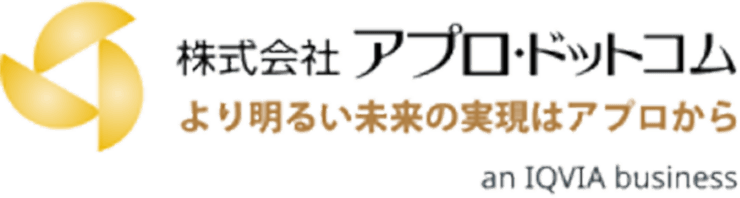
 はじめての方
はじめての方






 気になる求人
気になる求人