スタッフブログ
薬剤師の仕事・働き方・キャリアに関するトピックスから、最新の薬剤師求人、派遣や単発派遣に関する法律やルールまで。薬剤師の最新事情に精通したアプロ・ドットコムのスタッフが、就職・転職に役立つ記事を配信いたします。
薬剤師の仕事・キャリア
2025.03.05
薬局の生成AI活用で薬剤師の仕事はなくなる?

- 薬剤師
- 派遣
- 求人
- 仕事
- アプロ・ドットコム
- かかりつけ薬剤師
- 在宅医療
- 生成AI
- コミュニケーション
近年、急激な発展を遂げている生成AI。生活のなかでもAIを身近に感じる人も増えているでしょう。たとえば、OpenAI社の「Chat GPT」などは有名なので聞いたことがある人も多いかもしれません。
最近は、AIサービスが多様化し始めています。生成AIを業務システムに組み込み、「今まで人間にしかできなかった作業を自動化する」「業務効率化を図ったりする」など、仕事にも変化が起こっています。
しかし、生成AIが発展するにつれ、多くの業界で「AIに仕事が奪われるのでは?」「人間がやることがなくなるかもしれない」といった声が挙がり始めました。「薬剤師の仕事もなくなってしまうのではないか」「薬剤師の需要が減るのではないか」と不安に思っている人もいるかもしれません。
では、生成AIが活用されることで薬剤師の仕事にはどのような影響があるのでしょうか。薬局における生成AI活用について見ていきましょう。
目次
AIと生成AIの違い
生成AIという言葉を聞いて、ただのAIとは何が違うのか疑問に思う人もいるでしょう。AIはもともと決められた作業を自動で行うものでした。たとえば、機械やソフトウェアが学習や推論、問題解決、知識表現、認識といった人間のような知能を模倣する技術などが当てはまります。現在、検索エンジンや推薦システム(レコメンド)、自動運転車、音声認識、画像認識など、さまざまな場面で使われています。
一方で、生成AIは学習したパターンなどを活用し、新たなアイデアやコンテンツを作り出したり、問題を解決したりするもの。薬剤師の知識や対応方法などを学習させることで、より多くの業務を任せられるのではないかといわれています。
つまり、AIは広い概念であり、生成AIはその中の一部分と考えればわかりやすいでしょう。AIはデータの分析、解釈、予測などに向いており、生成AIは新しいデータやコンテンツの生成に特化しています。
生成AIが登場する前は「薬剤師業務の一部はAIに置き換わるとしても、対人業務の大部分は置き換わらない」と考えられていました。しかし生成AIには従来のAIには備わっていなかった社会的知能が備わっているため、現時点ではAIにできない対人業務も近い将来できるようになるかもしれません。
薬局でAIを利用するメリット
ここからは、薬局でAIを活用するメリットを紹介します。
・AIの活用によって対人業務の質を向上させられる
調剤業務や処方監査を行うAIを活用することで業務効率化が進むと、薬剤師が対人業務に充てる時間を確保できます。たとえば、かかりつけ薬剤師が患者様の服薬情報の一元的管理や継続的把握を担当すると業務量が増加しますが、AIが薬歴管理、知識の保管をしてくれれば余裕ができるため、質の高い内容を提供できます。
また、幅広い薬の知識を求められるようになった場合にも、服薬指導や薬歴用ソフトに導入されたAIを活用すれば、疾患や薬の知識を補完することができます。AIを避けるのではなく積極的に活用し、対物業務の時間を減らしながら対人業務にシフトすることで、今後も薬剤師として生き残れるでしょう。
・薬物相互作用のチェックができる
AIは膨大な医薬品情報をリアルタイムで解析し、処方薬の相互作用や禁忌、副作用のリスクを自動でチェックします。そのため、瞬時に薬物相互作用を検出して警告することが可能で、医療ミスの防止にも活用されるでしょう。
・薬剤師がスキルアップに注力できる
AIを活用して時間に余裕ができれば、薬剤師は専門性の高い業務により注力できるようになるはずです。具体的には、薬物治療の最適化や症例検討、研究活動など、より高度な業務を行えるようになります。
・リモート化と働き方改革の推進につながる
AIを活用すれば、薬剤師業務のリモート化も不可能ではありません。処方箋の電子化や遠隔服薬指導が普及すれば、薬剤師は薬局に常駐する必要がなくなるでしょう。在宅勤務やテレワークが広まれば薬剤師の働き方の選択肢が増え、ワークライフバランスの改善が期待できます。また、長時間労働の解消や休暇取得の促進にもつながるでしょう。
薬局でのAI利用の現状
ここからは、医療分野にも普及しているAIが現在薬局ではどのように活用されているのかを薬剤師業務ごとに解説します。
・調剤業務
調剤業務ではピッキングのほか、さまざまな工程でAIを活用しています。AI機能を持つ自動ピッキング装置では、レセコンから入力されたデータをもとに、払い出す薬剤を自動で集めるピッキング作業を正確で素早く行います。
また、人の手では不可能なスピードでピッキングすることができるため、患者様をお待たせする時間を減少させられるでしょう。製品によっては画像認識を活用したPTPシートの端数チェック、ピッキングした薬剤の数量チェックができる重量監査機能がついているものもあります。
・処方箋監査業務
薬や疾患に関するデータを学習したAIは、処方監査や疑義照会を正確に行うサポートをしてくれます。たとえば、添付文書上の禁忌にあたる場合、併用薬との相互作用が認められた場合にアラートで知らせることができ、「禁忌を見逃して薬を渡してしまった」などのミスを防ぐのに役立っています。
また、処方箋対応の経験を積んでいくうちに、「添付文書の用法や用量としては問題ないけれど、この量は不適切かもしれない」と疑問に思う場面が出てきます。そういった薬剤師の経験則による判断についてもAIはサポートしてくれます。
・服薬指導・薬歴業務
服薬指導や薬歴のソフトでもAIの製品が開発されています。AIが処方内容や薬歴を解析し、疾患を推測して指導内容を提案することによって、より良い質の向上が実現できます。指導すべき食事療法から生活上の注意点、季節性の体調変化まで、幅広い視点からAIが指導内容を提案するため、患者様に必要な情報を漏らさずに伝えられるのが特徴です。
また、音声入力を使えば、言葉を発するだけでテキスト入力が可能。タイピングが苦手な人や忙しい時間帯でも、スムーズに電子薬歴を入力できるのがメリット。薬歴の記入時間の短縮にもつながります。患者様との会話をそのまま文章化して登録するシステムも開発されており、さらなる業務効率化が期待できます。
AIによる改善や効率化が必要なもの
薬局の現状を踏まえたうえで、薬局において改善や効率化が必要なのは以下のようなものです。
・手作業での業務が多く、煩雑な作業の効率化
・医療過誤につながる人的エラーの防止
・地域における薬剤師人口の格差解消
・かかりつけ薬剤師など今までとは違った需要への対応
生成AIは薬剤師の仕事を奪うものではなく、これらの懸念点の強力なサポートになります。また、経験を積んだ薬剤師ならピンとくるような事項を生成AIに学習させれば、ベテランがいない職場でも適切な調剤ができるようになるでしょう。
薬局でのAI利用の将来
AIが登場した頃は、AIが行える薬剤師業務は対物業務など限定的であると思われていましたが、生成AIが出現したことで状況は少しずつ変化しています。いずれはAIもある程度の対人業務を行うようになる可能性が出てきたためです。しかし、そうなったとしても全ての薬剤師業務がAIに置き換わるとはいえないでしょう。では、なぜ薬剤師業務は生き残るのでしょうか。
・薬剤師の対人業務はAIに代替されにくい
近年、患者様の服薬について、多剤服用が有害事象の原因となるポリファーマシーが問題になっています。
厚生労働省発行の「高齢者の医薬品適正使用の指針」では、高齢者に6種類以上の投薬をしたことで有害事象の発生頻度が増加したという結果が出ています。ひとつの薬局が75歳以上の高齢者に7種類以上の薬剤を調剤したのは全体の24.8%であり、5種類以上の薬を調剤した割合は全体の41.1%という高い数字です。
2020年9月に薬機法が改正されたことで、服薬指導後の服薬フォローアップが義務化されました。薬剤師は薬を渡したあとの服薬状況や副作用について、患者様の状態を継続的にフォローしていかなくてはなりません。ポリファーマシー問題や服薬フォローアップなどの対人業務は、AIには代替されにくい能力を必要とするので、今後も薬剤師が行う可能性が高いでしょう。
・AIは責任が取れない
AIが生成する情報が間違っていたとしても、AIは責任を取ることができません。生成する情報の精度は今よりも高くなっていくと考えられますが、誤りがなくなることはないでしょう。誤った情報を信じた患者様に健康被害が生じた場合、責任を負うのは薬剤師になる可能性が高くなります。
AI時代にニーズの高い薬剤師とは?
AIの活用で便利になること、薬剤師の仕事が生き残ることを紹介してきました。とはいえ、今までと同じように薬剤師の仕事が残るわけではないでしょう。ここからは、AI時代でも必要とされる薬剤師はどのような人材なのかを見ていきます。
・コミュニケーションで共感や安心を醸成できる薬剤師
厚生労働省は薬剤師の仕事を「対物業務から対人業務へ」変換することを求めています。そのため今後は「対物業務」をAIが請け負うことが主流になっていき、薬剤師は「対人業務」で能力を発揮する必要が出てくるでしょう。在宅医療の推進により、かかりつけ薬剤師として働く人もさらに多くなると予想されています。
かかりつけ薬剤師として薬歴管理、服薬指導、服薬管理などを行う際に、毎回同じ対応をして、カルテと数字の管理をするだけならAIと同じです。対人業務が重要となる今後は、患者様との良好なコミュニケーションが求められます。安心感や信頼感を作り出し、ちょっとしたことを相談できるような関係性を作れる薬剤師が必要とされるはずです。
・在宅医療を行う薬剤師
日本は超高齢社会を迎えようとしており、在宅医療が薬剤師の重要な役割のひとつと考えられています。在宅医療は患者様の終末期に携わることも多く、AIが代替しにくい業務です。厚生労働省の報告によると、2019年度に居宅療養管理指導料を算定した薬局数は25,000件以上であり、将来的にも在宅医療の需要は伸びていくでしょう。そのため、在宅医療に積極的に関わる薬剤師が求められるようになるはずです。
・AIのアウトプットに対して正確性や倫理的な問題をチェックできる薬剤師
前述したように、生成AIの作り出す情報は完璧ではありません。現在はまだ、間違っている情報を当然のことのように伝えてくるケースも見受けられます。薬剤に関する情報が間違っていた場合、患者様の健康に影響が出る恐れがあり、大きなミスにつながることもあります。そのため、AIの情報を鵜呑みにせず、情報の正確性や問題点に気づき、しっかりと指摘し、適切な対応できる能力がある薬剤師が評価されるでしょう。
・AIを活用できる薬剤師
「対物業務」をAIに任せ、「対人業務」で力を発揮することが薬剤師には求められていきますが、生成AIは勝手に仕事をしてくれるわけではありません。対物業務について指示をするのは薬剤師です。薬剤師は取り扱う薬剤の種類や組み合わせなど、患者様に関わるすべての服薬情報をAIに伝え、適切に対応できるように育てる必要があります。このようにAIを正しく活用できる薬剤師が活躍するようになるでしょう。
薬剤師として今後も活躍したいなら「アプロ・ドットコム」をチェック!
今回は、生成AIが普及してもニーズがある薬剤師について説明しました。今後もAIの活用はますます増えていきそうで、これからも必要とされ続ける薬剤師になるためには、ぜひキャリアアップをめざしたいものです。
アプロ・ドットコムは薬剤師のマッチングに特化しており、25年以上の実績があります。ドラッグストアや薬局、病院の現状をよく知るキャリアアドバイザーが多数在籍しており、正社員、パート・アルバイト、派遣、1日から働ける単発派遣と、さまざまな雇用形態の求人を扱っています。
丁寧なカウンセリングによって、個々のめざすキャリアを理解したうえで最適な求人を紹介することが可能です。今後のキャリアが不安な方、薬局の採用の変化や求められる人物像について知りたい方は、アプロ・ドットコムにお気軽にご相談ください。
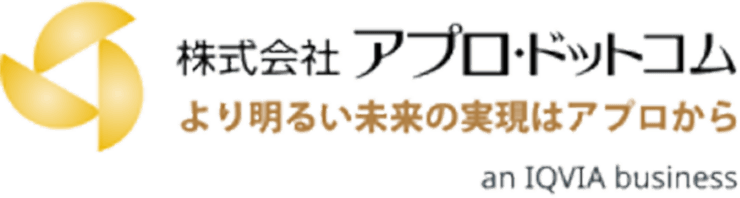
 はじめての方
はじめての方






 気になる求人
気になる求人